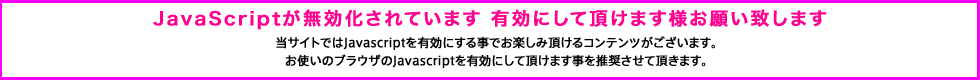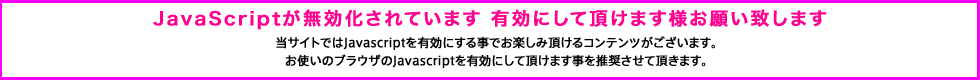夏の大阪は、毎日がお祭りだった
大阪大学招聘教授 高 島 幸 次

一言に「祭り」といっても、その様相は千差万別である。それが生まれた時代や地域、主宰者の立場によって、驚くほど多彩である。「天神祭」も「祭り」なら、過疎地の「村まつり」も「祭り」である。宮中の「新嘗祭」も、家庭の「ひな祭り」も「祭り」である。各地の観光的な「桜まつり」「雪まつり」や、商店街の「大感謝祭」だって「祭り」といえないことはない。まずは、この辺りから整理しておこう。

「祭り」は、第一義的には「神を祀る」ことである。神社で神職が行っている「神事」と同義と考えていい。その意味では、神社においては毎日「祭り」が行われていることになる。
|
しかし一般に、私たちが「祭り」という場合は、一年のうちの特定の日の行事を指すことが多い。天神祭の場合なら、神様が年に一度だけ、天満宮から外へ出て、「氏地の平安、氏子の無事」を見守るために巡幸される日を意味する。この特別な日には、氏子や崇敬者は神様の巡幸を慶んで、威儀を正した衣装を身にまとって先触れをしたり、あるいは美しく着飾ってお供の行列を組んだり、さらには笛・鉦や太鼓で囃したてて練り歩く。その結果、祭りの賑々しい雰囲気、いわゆる「お祭り騒ぎ」が生まれるのである。これを「神賑行事」という。 |
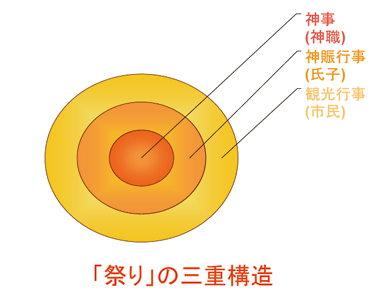 |
全国各地で行われている「祭り」の多くは、この二重構造からなっている。なかには、数社を兼務する神主によって行われる「神事」を伝えるものの、「神賑行事」が廃れ気味の地域もあるらしい。その反面、天神祭のような、ごく一部の大規模な「祭り」では、「お祭り騒ぎ」を見物するために、地域外から多数が訪れ、一層の賑わいを生み出している。これが「観光行事」である。ここに三重構造が成立する(図)。
先に述べた通り、「祭り」の第一義的な意味は「神事」だが、世間的には、「神賑行事」「観光行事」の賑わいこそが「祭り」だととらえる傾向が強い。そこで、同様の賑わいを期待して、地域活性化のための「雪まつり」や「桜まつり」、商店街の「大感謝祭」などが企画されるのである。図でいうなら、真ん中の「神事」のない、ドーナッツ型の二重構造の「まつり」だ。
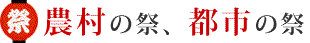
「雪まつり」や「大感謝祭」などはさておき、全国各地で伝統的に行われている「祭」の起原は、大きく「春祭」「夏祭」「秋祭」に別けられる。このうち、水田稲作の豊穣を祈る「春祭」と、収穫を感謝する「秋祭」は、いうまでもなく農村社会から生まれた。住吉大社の「御田植神事」は、その代表例といえよう。
これに対して、都市社会では、疫病に対する畏怖の念から、その退散を祈る夏祭が生まれた。農村の生活は、周辺に広がる豊かな大自然の浄化作用に守られ、低い人口密度であったため、疫病の流行は限定的だった。ところが、自然を切り開いた人工的な空間に、数多くの人々が密集して暮らし始めると、排泄物の処理設備が不十分であったこともあり、疫病の流行が最大の脅威になった。そこで古代社会における唯一の都市ともいえる宮都では、毎年の6月と12月の晦日に、その四隅の進入路上で疫神を退散させるための「道饗祭(みちあえのまつり)」が行われた。現在、大阪天満宮の境内に祀られる摂社・大将軍社は、難波長柄豊碕宮(652~686年)の西北の路上で行われた道饗祭の由来を伝え、今も年2回の道饗祭を伝えている。
実は、この6月と12月の晦日は、律令制下の朝廷において「大祓(おおはらえ)」が行われた重要な日であった。年2回の「大祓」は、万民の罪穢を祓い除き、清浄にするための神道儀礼であるが、このうち6月晦日の「大祓」は、「夏越の祓え」の名で民間にも受け継がれた。ちょうど一年の半分を過ぎる時期にあたり、気温も湿度も高くなり、疫病の流行が心配される季節であるため、特に都市民には、その重要性が痛感されたに違いない。「夏越の祓え」では、形代(かたしろ)に半年間の罪穢れを託して川に流し、災厄除けのために茅の輪をくぐることが一般的だった。やがて、都市の形成に伴う疫病退散への関心の高まりは、この「夏越の祓」に習合されて、都市型の「夏祭」を生み出すことになるのである。
現代に伝わる大規模な祭は、天神祭だけではなく、京都の祇園祭や、東京の神田祭・山王祭など、全て「夏祭」であるが、それは「神賑行事」の盛んな都市の祭りに由来するからである。
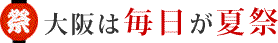
江戸時代の大坂は、我が国有数の都市に発展したから、疫病流行への不安も尋常ではなく、市中各地で「夏祭」が相次いだ。江戸中期の池田正樹『難波噺』によれば、旧暦6月の大坂では下記のような夏祭が行われていた(カッコ内は現在の寺社名)。
- 1日 愛染明王(愛染堂・勝鬘院)
- 13・14日 難波祇園祭礼(難波八阪神社)
- 14日 住吉神輿洗ひ(住吉大社)
- 14・15日 島之内八幡(御津八幡宮)
- 16・17日 御霊宮初事(御霊神社)
- 17・18日 高津宮(高津宮)
- 20・21日 船場稲荷(難波神社摂社の博労稲荷神社)
- 21・22日 座摩宮(坐摩神社)
- 24・25日 天満天神(大阪天満宮)
- 27・28日 生玉明神(法安寺)・森の宮(鵲森宮)
- 29・30日 玉祭稲荷(玉造稲荷神社)・住吉祭(住吉大社)
これは、当時の「大坂三郷」の祭に限られるから、現大阪市域でいえば、杭全神社(平野区)などの夏祭が抜けている。ちなみに、昭和12年(1937)の上田長太郎『大阪の夏祭』には、新暦7月8日から8月1日までに行われる100ヵ所の夏祭一覧が掲げられている。まさに、夏の大阪は毎日が夏祭だった。
なお、これら夏祭のほとんどは、「神事」と「神賑行事」の二重構造からなっていたが、「天神祭」の場合は、すでに江戸時代中期には、各地から観光客が訪れ、三重構造に発展していたのである(その様子について「天神祭の観光化」を参照のこと)。
|